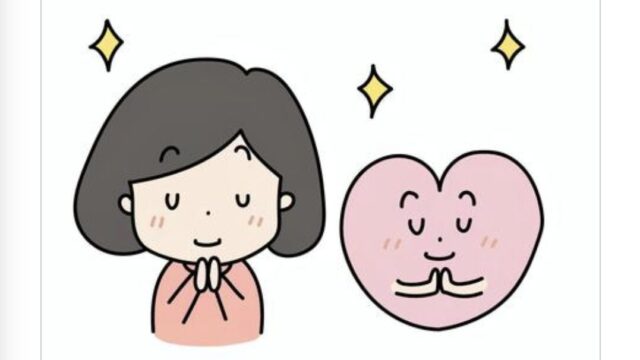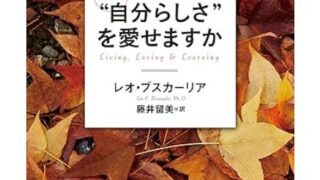7つの原型(アーキタイプ)
7つの原型(アーキタイプ)
「7つの原型(アーキタイプ)」
についてお話していきますね。この7つの原型とは、
転生を経ても変わらない、核となる魂の役割・動機を現す部分です。
たとえば、占星術には、まず12の「太陽の星座」がありますね。「エニアグラム」という人格の特徴を分析するツールには、9つの原型(アーキタイプ)があります。
それと似ていますが、
魂の構造のなかの「原型(英語でアーキタイプ)」は、
地上での一転生の人格を現すのでなく、
いくつもの転生を通して、変わらない、まさに霊魂の「核(コア)」の波動を成すものです。
原型(アーキタイプ)には、7つがあります。
「賢者」
「職人」
「僧侶」
「奉仕人」
「王」
「戦士」
「学者」
の7つです。
※どの原型(アーキタイプ)を核として持つのかは、霊魂が生まれ出たそのときの「源」の「波動」が関係してきます。
7つの原型(アーキタイプ)に話を戻します。
それぞれの原型(アーキタイプ)は、転生を通して、全体のなかでどのような役割、動機を負っているか、を示すものであり、「職業」ではありません。
なので、「僧侶」でも、転生して何度も「僧侶」になることもありますが、必ずしも現実に「僧侶」でないと僧侶の役割を果たせないわけではありません。「戦士」だからといっていつも「戦士」という職についているわけではありません。
あくまで、その性質、その役割を、「全体のなかで帯びている」ということなのです。
原型の役割とは何なのか?
具体的に、お話していきましょう。
賢者
「賢者」
たとえば「賢者」は、知恵を伝える人、教える人、表現する人。何かを常に伝えたい、表現したい、人に関わっていきたい人々です。
ですから、基本的に話すことや書くこと、コミュニケーションに対する意欲が高く、伝えたい、という動機を強くもっています。
この「賢者」がコアの人は、どのような職業についているのであれ、人生や仕事や出来事から得られた「学び」「気づき」つまり「知恵」「経験」「洞察」を、人にシェアしていきたい、伝えていきたい、役立てたい、表現したい、という動機をもっています。
どのような職業についているのであれ、です。
たとえば、オフィスで働いているサトシさんは、いつも周りの人々や上司などの様子を熱心に観察しています。周りの人たちが上司とうまくいかない、上司の言うことがよくわからない、といった状況があったとします。
「賢者」であれば、
「人事部で悩んでいるタカハシさんはこういう考え、あの上司はこういう人、以前こういう出来事があったとき、うまく切り抜けたエリカさんがいたなぁ。こういう上司には、エリカさんがしたように、こまめに報告をして相談して、頼りにしていますというスタンスで臨めばもっとうまくいくんじゃないかな。最近読んだ本で、そういえばちょうどいい事例や対処法が載ってたな・・・」
などと気づいて、それをタカハシさんに伝えようとするかもしれません。あるいは、周りの人たちや本人との会話の中で聞かれれば、「洞察」「知恵」「経験」を周りの人たちにシェアすることでしょう。
人に関しても、状況に関しても、表面の奥深いところにある本質や真実を見ようとする、そして得られた気づきや知恵を「表現したい」「伝えたい」という動機を持つのが「賢者」の特徴です。
その特徴から、人に伝えること、表現すること、書くこと、話すこと、教えること、を本職にする人も、確かに多いです。が、職業に限定されるものではありません。
あくまで、
原型・アーキタイプ > 職業
なのですね。
ですから、どの職場にも、どのクラスにも、どのグループにも、「賢者」のコアをもつ人がいます。
いつも何か伝えたい、いつも何か知っていてそれを人と分かち合いたい・・・といった人は、いませんか?
職人
「職人」の原型(アーキタイプ)
「職人」はこれまでにない何かを創り出すこと、「創造性」を発揮することで全体へ役立ちたい、リードしたい、という動機を持つ人々です。
ですから基本的に、
創り出したい、工夫したい、新しいもの、他にないものを生みだしたい、という動機を強くもっています。クリエイティブ、ということです。
この「職人」がコアの人は、どのような職業についているのであれ、
「自分だったらこうするのに」「不便だな。ここもっとなんとかならないかな」「こういう便利なものがあったらいいのに」「もっと便利なもの、美しいものにできるのに、すればいいのに」などと、感じます。
どのような職業についているのであれ、です。
たとえば、歌手で「職人」がコアの人は、歌唱技術を高めることや、さまざまなジャンルの「これまでにない」組み合わせの斬新な曲を創り出すことに熱中、集中するかもしれません。
芸術、建築、料理なども、創造性・新しいものをを創りたい、生み出したい、という「職人」ならではの欲求を発揮しやすい職業です。
古くは馬車、洋服、現代ならIT機器や車、宇宙、医療技術、
「これまでよりもっとよい」「今までにない」発明、技術、発想で新しい便利なもの、よりよいもの、スペックのいいもの、美味しいもの、よりよいサービスを作ることに生涯をささげる「職人」たち。見つけることはとても簡単ですね。
魂の年齢が古くなっていくと、より抽象的なものを生みだす、創造したいと願うようになるでしょう。たとえば、サービス、コミュニティ、仕組みなど。
とはいえ、あくまで
原型・アーキタイプ > 職業
なので、「生み出したい」動機があって、それを満たすこと。それが結果として職業につながってくる、ということです。
職人の人たちは「何かを創り出すこと」に熱中しているときが幸せ。
ですから、どの職場にも、どのクラスにも、どのグループにも、「職人」のコアをもつ人がいます。
周りに、いつも何か造っている、新しい何かを発明している、ネタを考えている、いつも何かを創りだすことに熱中していたり、工夫したりしている人は、いませんか?
発明品、技術、作品、仕組み、コミュニティ・・・
アート・ファッション、テクノロジー、料理など、実業の世界は、このような人で溢れています。
作品、製品、商品を生みだして利益を生みだす、経済をけん引する人々、と言ってもよいかもしれませんね。
何であれ、「職人」の人々は自分にしかできないものを、創造性を発揮して創り出す、生みだす、全体へ、そのようにして役立ちたい、リードしたいという動機を強く持っているのですね。
僧侶
Vol.251 7つの原型―解決し導く「僧侶」
+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+
さて、7つのアーキタイプ、初日は「賢者」2日目の昨日は「職人」についてお話しました。
「職人」は新しい何かを創造性をもって生みだし、全体へ役立ちたいという動機をもつ人々でした。
では、「僧侶」の原型(アーキタイプ)の役割、動機は、何でしょう。
「僧侶」の原型(アーキタイプ)
「僧侶」は愛をもってインスピレーションを与え、人々が可能性を発揮できるよう導きたいという動機を持つ人々です。
ですから、
愛したい、与えたい、育てたい、(問題や障害を)解決したい、世話したい、という動機を強くもっています。
この「僧侶」を核(コア)にもつ人は、どのような職業や社会の階層にいるのであれ、
周りの人々のよりよい姿を望み、「こうしたらもっと楽になるのに」「可能性を発揮できるよう手助けしたい」「もっと愛ある世界にできるはず」などと、感じます。
どのような職業についているのであれ、です。
もちろん、本職が「僧侶」の人々で、魂の原型・役割を「僧侶」にもつ人々もいますが、
現実に「僧侶」職であっても、「王」として支配する、リーダーシップを発揮する役割をもつ人々もいます。
また、現実に「僧侶」職であっても、既成の枠組みに果敢に挑戦したり、新たな分野を開拓していく「戦士」の原型・役割をもつ人々もいるでしょう。
とくに、分野としては、教育、セラピスト、カウンセラー、コーチ、医療関係者、スピリチュアル関連などでは、「僧侶」をコアに持つ人が非常に多くなります。(が、繰り返しますが、皆が僧侶の原型をもつわけではありません。)
それはきっと簡単に想像できますね。
人々を癒したり、話を聞いたり、解決方法を示したり、よりよい世界を創造したいと願う人々ですから、勝又伸子さんご自身もこの原型をお持ちかもしれないし、周りの人々にもそういう人が多いかもしれません。
「僧侶」の原型を持つ人々は、そのような仕事についている人が多いとはいえ、やはりこちらも職業に関わらず、です。
オフィスの仕事であれ、工場の仕事であれ、などとどこにいても「人」に強い関心を持ちます。
家族をもっと幸せにしたいと料理に勤しむママや、社員が力を発揮して皆が幸せに暮らせるよう心を砕く現場仕事のリーダーもいるでしょう。学校の先生や、職員の人の中にもいるでしょう。
人々がポテンシャル(可能性)や力を発揮して、幸せなよりよい世界を創りたいと尽力する「僧侶」たち。見つけることはとても簡単ですね。
魂の年齢が古くなっていくと、日常的な事柄を超えて、より高次の可能性を発揮することを求めるようになるでしょう。
ですから、どの職場にも、どのクラスにも、どのグループにも、「僧侶」のコアをもつ人がいます。
周りに、いつも皆の可能性、善性を発揮しようと、人を鼓舞するグループのリーダー、先生、コーチ、教育者を見かけませんか?あるいはそのような人物を思い出せませんか?
とくに教育関連、医療関連、サービス関連の世界には、このような人が大勢います。音楽家で「音楽を通して人の可能性を引き出し、世界を平和な場所にしたい」と望む人もいるでしょう。
であるから、やはり
原型・アーキタイプ > 職業
なのですね。
原型・アーキタイプは、根源的な動機の部分を現します。
何であれ、「僧侶」の人々は、
人を愛し、癒し、育て、平和な世界を創ろうと尽力する、そのようにして全体に対して役立ちたい、リードしたいという動機を強く持っているのですね。
奉仕人
+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+
Vol.252 7つの原型―役立ち献身する「奉仕人」
+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+
さて、7つのアーキタイプ、「賢者」「職人」「僧侶」についてお話ししてきました。
今日は「奉仕人」です。
奉仕人は常に役立つこと、自分が何か「善いこと」に役立ちたい、「仕えたい」という動機をもつ人々です。とても忠実な人々でもあります。
「奉仕人」の原型(アーキタイプ)の役割を詳しく見ていきましょう。
「奉仕人」の原型(アーキタイプ)
「奉仕人」は人々や善いことにたいして、喜びをもって、奉仕したい、役立ちたい、仕えたい、という動機を持つ人々です。
ですから、
全体の中で、実際に体を動かし、何か「善いこと」「役立つこと」に従事したり、仕えているとき、最も活き活きする人々で、人が喜んでくれると、喜びが大きくなります。
この「奉仕人」を核(コア)にもつ人は、どのような職業や社会の階層にいるのであれ、周りの人々や全体に対して奉仕すること、役立つことを望みます。
実行に移し、行動に移す人々です。そして自身の奉仕や行動が、よりよい結果につながったのを見る時、心から喜びを感じるのです。
ゆるぎない奉仕への確信と喜びをもって、実行する人もいるでしょう。
この「奉仕人」も、どのような職業にでも存在します。
この原型・アーキタイプはもともと英語で「奴隷」とありましたが、それだと本当の意味をうまく表せていないと感じるので、私は「奉仕をする人」という表記を採用しています。
「奉仕人」というと低位の職業と思われがちかもしれませんが、「神・仏への奉仕」「しもべ」という謙虚さ、信心から僧侶や神父を本職とする人々もあるでしょう。(そう言葉で言っていても動機がそこにはない場合も多々あります)
意外に思えるかもしれませんが、
たとえば技術や教育を本職とする「奉仕人」の原型をもつ人がいたとすれば、
技術や教育という職、そしてそれが影響を及ぼす世界や、関わる人々に対して、自分のできることに黙々と貢献しようとするでしょう。
「奉仕人」の原型・アーキタイプを持つ人々は、「奉仕」自体に意味を求め、意義を感じるので、静かで黙々と自身のやるべきことに取り組む人も多いのです。
すると何が起きるでしょう?
有言か無言かに関わらず、コツコツ「実行」するので、様々な事柄を「達成」することになります。その「達成」は「奉仕」に没頭した結果。
ということで、淡々とその「職務」「奉仕」へ献身し、努力し続ける、その一貫した態度・行動が「信頼」されやすく、
「実行」「積み重ね」「信頼に値する」人々として、周りから一目置かれたり、他の人が「とても自分にはできない・・・」と思うような結果にたどり着くのです。
そんな「積み重ね」が上位や周りの人々からの評価や、信頼を置かれることにつながると、
突如として引き上げられたり、引き立てられたり、信任されることもあるでしょう。
「奉仕人」は人々や善いことにたいして、喜びをもって、奉仕したい、役立ちたい、仕えたい、という動機を持つ人々ですから、どの分野にも数多く存在します。
公共サービス、ボランティアの分野では、とても容易に見つけることができます。公務員、施設、秘書、執事、サービス業、僻地の医師や技師、献身的な社員や職員、世話人、守る人、弁護する人、・・・など。
人々の集まるところにはこの「実行者」として「献身的に動く」役割をもつ「奉仕人」が大勢存在しており、
むしろこれらの「奉仕人」の人々の「実行力」なしには、物事は進んでいかない、とさえいえるのです。
黙々と努力する、ひたすら人や分野や世界の役に立ちたいと願い、献身的に日々の「役割」にいそしむ人々、それが「奉仕人」の原型・アーキタイプの特徴です。
人当たりのよい、真面目な人、努力家、献身的な人。そういう人が周りにいませんか?
王
王は常にリードしたい、率いたいという動機をもつ人々です。存在感がありパワフルな原型・アーキタイプでもあります。
「王」の原型(アーキタイプ)の役割を詳しく見ていきましょう。
「王」の原型(アーキタイプ)
「王」は基本的に、リードしたい、率いたい、掌握したい、という動機を持つ人々です。
ですから、
人々と交流し、全ての情報を把握し、自らが引率することに力を注げます。この「王」を核(コア)にもつ人は、どのような職業や社会の階層にいるのであれ、全体を見渡して、リーダーであろうとし、リーダーシップを発揮しようとします。
そして、そのやりとりがうまくいって、人々が思うとおりに動いてくれること、同意してくれること、自身をリーダーとして認めてくれることを期待します。
この「王」も、どのような職業にでも存在します。
「王」の原型・アーキタイプを持つ人は、存在感があります。パワーを感じさせる人々で、周りは、どこかこの人に従わなくてはいけないような気になりやすいのです。年齢が古くなってくると「王」には、真のリーダーシップが備わってきます。
様々な職業に存在しますが、ことにイメージしやすいのは、経営者、役員、政治家、チームのキャプテンなど。
ということで、他の原型・アーキタイプに比べると少数と言えるかもしれません。とくに先の「奉仕人」は圧倒的な人数があるのと比較すると、支配、管理、引率する人は、数が多くないのが自然です。
「王」は人々にたいして、率いたい、管理したい、率いたいという動機を持つ人々ですから、そのために払う努力も相当のものになります。
率先して、グループのたとえば班長に立候補したり、あるいはしたいと思ったり、全体の取り仕切り役を買ってでたり。調整役をしたり、交渉をしたりすることもあります。
それは、自分のグループ、組織、国を運営したい、指示したい、管理したい、率いたい、という根源的な欲求があるからです。
どこにもリーダーは必要で、そのリーダーの性質が、その構成員、周りの対外的なやりとりの質に大きく影響します。
大勢の人を率いるのに、風格、人格、経験、資質を備えたリーダーであればよいですが、偏った思想の持ち主であったり、パワーをもって自分の思い通りに人に影響を与えたい、となったとき「王」は「暴君」になる可能性があるのですね。
どの原型・アーキタイプにも、ポジティブな面、ネガティブな面とありますが、ことに「王」はリーダーシップを発揮したい、根源的な動機をもつので、他者に対する影響が大きくなりやすいのです。
周りを見回していただいて、王様タイプの人はいませんか?
年齢が古くなると成長を遂げ、その「リーダーシップ」の現れ方はより成熟したものになり、「よりよく統治する王らしい王」「周りのグループ・組織とも上手につきあいながらそのグループを構成する人々に幸せや平和や豊かさなどよいものをもたらそうと専心する」ようになるでしょう。
場合によっては、勝又伸子さんご自身もこの原型をお持ちかもしれないし、周りの人々にもそういう人がいらっしゃるかもしれません。
数は多くないにしても、たいがいの組織・グループ・国に「王」の原型・アーキタイプの人はいますから、見つけることは難しくはありません。
「王」の原型を持つ人々も、「職業に関わらず」です。繰り返しますが、どの職場にも、どのクラスにも、どのグループにも、「王」のコアをもつ人がたいがいいます。
原型・アーキタイプ > 職業
でしたね。
いろいろな意味で、パワフルで、存在感のある人々です。
明日は、「戦士」の原型(アーキタイプ)について、お話していきますね。
戦士
Vol.250 7つの原型―開拓し達成する「戦士」
+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+
さて、7つのアーキタイプ、「賢者」「職人」「僧侶」「奉仕人」「王」についてお話ししてきました。
「王」はリードしたい、管理したい、という動機をもつ人々でした。
では、「戦士」の原型(アーキタイプ)の役割は、何でしょう。
「戦士」の原型(アーキタイプ)
「戦士」は開拓したい、達成したい、勝ち取りたい、という動機を持つ人々です。
この「戦士」がコアの人は、どのような職業についているのであれ、
「もっと上を目指そう」「ここまで到達したい」「あの向こうへ行ったらどんな世界が拓けるか」「栄誉(や賞やポジションや立場)を勝ち取りたい」といった動機、ガッツを持っています。
戦士の場合も、どのような職業でも、となりますが、その特徴から、
競争心や鍛錬を発揮できる場を求めていきやすいと言えます。「諦めずに果敢に挑戦し続ける」という強さもあります。
古い時代は、家族や民族や国を守る、戦士という仕事が多くあったことでしょう。しかし、肉体的に戦うだけでなく、もっと複雑に、アイデアや弁論で、世界のマーケットで戦ったり立場を守ったりする「戦士」もあるでしょう。
「さらに先へ、前へ、到達したい」「他の人が見たことのない地を開拓したい」「ポールポジションをとりたい」「勝利を勝ち取りたい」
バイタリティに溢れて、戦いつづける人、達成しつづける人、果敢に攻める人、自身が大切にしている価値に対して「忠実」に働く人、現代にも「戦士」たちを見つけることはとても簡単です。
魂の年齢が古くなっていくと、単に達成してその栄光の座を手にしたい、褒賞を得たい、というだけでなく、何らかの貴重な価値を守るための戦いや、非暴力の戦いに身を投じる、何らかの高邁な目的のために戦う、という戦士もあるでしょう。
職業的には、さまざまですが、たとえば、スポーツ、消防士や警察などにも多くの「戦士」の原型・アーキタイプの人々が存在しますが、会社の中にも大勢の企業「戦士」がいるでしょう。
とはいえ、あくまで
原型・アーキタイプ > 職業
なので、「達成したい」「勝ち取りたい」といった動機があって、それを満たすことを必要とします。それが、職業であれ、人生であれ、なのですね。
戦士を原型・アーキタイプにもつ人たちは「戦略をたてたり、達成までの道のりを検討し、そこに一心に向かっていくこと」に熱中しているとき、そして努力に見合う「報酬」を勝ち取ったときに幸せを感じます。
ですから、どの職場にも、どのクラスにも、どのグループにも、「戦士」のコアをもつ人がいます。
周りに、いつも常に挑戦し続けている人、勝つために努力している人、特定のポジションをとるため、達成するために走り続けている、まさに「戦い続けている」人はいませんか?
競争心を発揮しないとできないような職業や分野には、戦士を見つけることが容易いでしょう。
何であれ、「戦士」の人々は、自分にしかできない努力を重ねてポジションを得る、達成する、そのための道筋を進み、開拓していく、全体へ、そのようにして役立ちたい、その役割をもってリードしたいという動機を強く持っているのですね。
明日は、7つめの最後となりました「学者」の原型(アーキタイプ)を持つ人についてお話していきますね。
学者
+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+
Vol.255 7つの原型―収集して分析する学者」
+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+
さて、7つのアーキタイプ、「賢者」「職人」「僧侶」「奉仕人」「王」「戦士」についてお話ししてきました。
「王」は率いたい、管理したい、という動機をもつ人々でした。
では、「学者」の原型(アーキタイプ)の役割は、何でしょう。
「学者」の原型(アーキタイプ)
「学者」は知識を集めたい、実験したい、試してみたい、調べたい、という動機を持つ人々です。
この「学者」がコアの人は、どのような職業についているのであれ、
「もっと知りたい」「どうなっているのか調べたい」「集めて理解したい」「試したい」「観察したい」「検証したい」といった動機、探究欲を持っています。
学者の場合も、職業に限られないことはほかの原型・アーキタイプと同様です。
学者の大きな特徴としては、探究欲がつよく物知りなことと、中立的です。なかには「この人は歩く辞書?」(いまの時代は)「歩くグーグル?」という人もいるでしょう。
ほかの原型・アーキタイプのやることを公平によく観察していて、分析することもあります。公平で客観的になりやすい反面、ものごとや情報の十分奥深くまで探究しない場合は、理解や知識の階層が浅くなることもあります。
たとえば、地図を作る、測量する、植物を採集して図鑑にする、地質を調査する、天文観察をする、他民族の動向や文化を理解するためにそこへ行って交流して記録する、ITをつかって情報を収集する…
知識を集めるだけでなく、分類したり、吟味したり、実際に確かめてみたり、分析したり。
そのため、客観的に全体を観察することが必要となってくるので、他の原型・アーキタイプの人々から少し距離をとっているように見えることもあるでしょう。「学者」たちは数がとても多いというわけではありませんが、必ずそういう原型・アーキタイプの特徴をもつ人々を見つけることができます。
魂の年齢が古くなっていくと、現象や情報のなかでも、日常的な現象の世界を超えて、未知の世界、深い知識や観察、古代の・・・未来の・・・ミクロレベルの・・・真理の・・・といった未知の領域へ探究・研究の範囲が広がっていくでしょう。
学者の原型・アーキタイプの職業もさまざまで、もちろん研究者、科学者、の人たちのなかにも多いのですが、(情報や知識などの)収集、分析家、編纂する人など、
基本的に情報を集め、検証し、知識をまとめたい人々です。
あくまで
原型・アーキタイプ > 職業
なので、「もっと知りたい」「どうなっているのか調べたい」「集めて理解したい」「試したい」「観察したい」「検証したい」といった動機があって、それを満たすことを必要とします。それが、職業であれ、人生であれ、なのですね。
学者を原型・アーキタイプにもつ人たちは「情報を収集し、人やものごとを観察し、分析したり、分類したり、それらへの理解が得られる」ことに熱中しているとき、幸せを感じます。
ですから、どの職場にも、どのクラスにも、どのグループにも、「学者」のコアをもつ人がいます。
周りに、いつも常に客観的にものごとを観察している人、何か聞くとたいがいの答えが返ってくる人、ものごとを徹底的に調べ上げて、周りの人から「歩く辞書」と言われているような人はいませんか?
一見地味で、静かに見えがちですが、注意をして「観察」してみると、常に淡々として周りを「観察」しているようなタイプの人が容易に見つかるでしょう。
学者は、究極的には全体に対してそのようにして役立ちたい、その役割をもってリードしたいという動機を持っているのですね。
簡単に7つの原型・アーキタイプを説明してきましたが、明日は、原型・アーキタイプについての説明を、もう少し詳しくしていきますね。
「魂の原型・アーキタイプ」を学ぶとき、しばしば皆様からいただく質問があります。ですのでそういったよくある質問への回答も含めながら、説明をしていきますね。
+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+
Vol.256 7つの役割―アーキタイプを分かりやすく
+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+
「7つの原型(アーキタイプ)」 (転生を経ても変わらない、核となる魂の役割・動機)
「賢者」「職人」
「僧侶」「奉仕人」
「王」「戦士」
「学者」
について、お話してきました。
この原型・アーキタイプですが、
たとえば「賢者」は情報・知識・知恵などを「広めたい」「伝えたい」「教えたい」という動機をもっています。
誰でも伝えたい、と思うことは普通にありますよね。ですので、誰でも「賢者かな?」と思うかもしれません。
ですので、すぐに「賢者」と思う前に・・・
さまざまな活動の種類があって、賢者の原型・アーキタイプを持つ人は、どのような活動をしているときであれ、底辺に「伝えたい、教えたい、広めたい」という動機を持っています。勿論それが不適切な状況や、大事なことでないならば、その動機は顔を出さないこともあるでしょう。
が、原型・アーキタイプは、その魂の生涯を通して、そして転生を通して、「動機」となる強い影響を与えるものですので、大事なことに取り組んでいるときはもちろん、人生を通して、その「動機」が表出しやすいのです。
原型・アーキタイプは全体の中で「役割」を表しもしますので、社会全体を見回して、「このような役割を担う人々」という特徴を見出すことができます。
写真を撮る、文章を書く、ということを例に使って、対比してみましょう。
賢者なら
たとえば「写真を撮る」にしても「写真を撮って何かを伝えたい。写真をとることで、知識や知恵や情報を伝えたい、表現したい。」
「文章を書く」にしてもたとえば「文章によって知恵を伝えたい」「コミュニケーションをよりよくする方法を知ったからそれをシェアしたい」・・・
職人なら
「独自の構図で、カメラの性能を完全に活かして、いかに上手な写真を撮るか」「作品として優れたもの・個性的なもの・芸術的なものを生みだしたい」
「文章を書く」ということの「芸を極めたい」「独創的なスタイルで作品を生みだしたい」「創り出したい」・・・
僧侶なら
「人の心に訴えかけて、愛やインスピレーションを喚起させるような写真」「人の可能性を引き出す写真」を撮りたい・・
「文章によって、解決を手助けしたい」「勇気を与えられたり、励まされるような文章を書きたい」
奉仕人なら
この写真を撮ることで「役に立ちたい」、撮影チームの一員として「手伝いたい」「役立ちたい」
たとえば大量の翻訳を一所懸命こなして「役立ちたい」「助けになりたい」「手伝いたい」
王なら
写真を撮るのに最善の人々と「交流し」「チームを作り」、各自のポジションと行動を「指示し」「率いたい」
文章を書くことで「いかにチームや組織を治めるか」、それにより繁栄のための道筋を「統制する」「率いたい」
となるでしょう。(例えば、です。)
勿論、人により状況によりケースバイケースです。この原型・アーキタイプだけですべてが決まるわけではないのですが。それでも「原型・アーキタイプ」と呼ばれるだけあって、この部分が人格にかなりの影響を及ぼします。
さて、ここまで、4つの原型・アーキタイプを、写真や文章を例にして、特徴を描いてみました。
「原型・アーキタイプ」は、写真を撮る、文章を書く、という異なった種類の「行動」を意味するのではなく、
「動機」を表現します。それは全体の中でになっている「役割」でもあります。
これらの異なる動機・役割をもつ魂が集まっているのが社会です。
それを分かりやすく描くために、「山登り、キャンプをする」ことを考えてみましょう。
「目的地についての情報」を賢者が集めてくると、王は「ルートを確定するのは戦士の〇〇、食料調達は奉仕人の△△」などと「適材適所に配置」しようとし、職人は「山登りとキャンプのための道具、どんな装備が必要か」を考え始め、
僧侶は「誰にとってもよい体験になるように配慮」しようとし、奉仕人は「食料や水などを確保」しようとするでしょう。戦士は「周りが安全か、ルートはどれが一番よいか」を確認しに外へ行き、学者は「あそこであれをやるのは非効率だな。やること観察したことすべてを記録しておこう」と考えるでしょう。
これが「原型・アーキタイプ」があらわす「役割」でもあります。
そのようにして、原型・アーキタイプというのは、人生を通して、転生を通して、その人の動機・役割の底辺に流れるもの、と言えるのですね。
原型・アーキタイプのほかに
「魂の構造」には
「7つのゴール」(今世の霊的な目的・ゴール・フォーカス)
「7つのモード」(今世の性格的資質)
「7つの態度」(経験を処理する方法)
「7つのセンター」(通常の感覚/サイキックセンス)
「7つの錨」(生命の損失を防ぐ安全策)
「7つの魂の年齢・段階」 (前にお話したものです)
があります。
+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+
Vol.256 7つの役割―アーキタイプを分かりやすく
+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+
「7つの原型(アーキタイプ)」 (転生を経ても変わらない、核となる魂の役割・動機)
「賢者」「職人」
「僧侶」「奉仕人」
「王」「戦士」
「学者」
について、お話してきました。
この原型・アーキタイプですが、
たとえば「賢者」は情報・知識・知恵などを「広めたい」「伝えたい」「教えたい」という動機をもっています。
誰でも伝えたい、と思うことは普通にありますよね。ですので、誰でも「賢者かな?」と思うかもしれません。
ですので、すぐに「賢者」と思う前に・・・
さまざまな活動の種類があって、賢者の原型・アーキタイプを持つ人は、どのような活動をしているときであれ、底辺に「伝えたい、教えたい、広めたい」という動機を持っています。勿論それが不適切な状況や、大事なことでないならば、その動機は顔を出さないこともあるでしょう。
が、原型・アーキタイプは、その魂の生涯を通して、そして転生を通して、「動機」となる強い影響を与えるものですので、大事なことに取り組んでいるときはもちろん、人生を通して、その「動機」が表出しやすいのです。
原型・アーキタイプは全体の中で「役割」を表しもしますので、社会全体を見回して、「このような役割を担う人々」という特徴を見出すことができます。
写真を撮る、文章を書く、ということを例に使って、対比してみましょう。
賢者なら
たとえば「写真を撮る」にしても「写真を撮って何かを伝えたい。写真をとることで、知識や知恵や情報を伝えたい、表現したい。」
「文章を書く」にしてもたとえば「文章によって知恵を伝えたい」「コミュニケーションをよりよくする方法を知ったからそれをシェアしたい」・・・
職人なら
「独自の構図で、カメラの性能を完全に活かして、いかに上手な写真を撮るか」「作品として優れたもの・個性的なもの・芸術的なものを生みだしたい」
「文章を書く」ということの「芸を極めたい」「独創的なスタイルで作品を生みだしたい」「創り出したい」・・・
僧侶なら
「人の心に訴えかけて、愛やインスピレーションを喚起させるような写真」「人の可能性を引き出す写真」を撮りたい・・
「文章によって、解決を手助けしたい」「勇気を与えられたり、励まされるような文章を書きたい」
奉仕人なら
この写真を撮ることで「役に立ちたい」、撮影チームの一員として「手伝いたい」「役立ちたい」
たとえば大量の翻訳を一所懸命こなして「役立ちたい」「助けになりたい」「手伝いたい」
王なら
写真を撮るのに最善の人々と「交流し」「チームを作り」、各自のポジションと行動を「指示し」「率いたい」
文章を書くことで「いかにチームや組織を治めるか」、それにより繁栄のための道筋を「統制する」「率いたい」
となるでしょう。(例えば、です。)
勿論、人により状況によりケースバイケースです。この原型・アーキタイプだけですべてが決まるわけではないのですが。それでも「原型・アーキタイプ」と呼ばれるだけあって、この部分が人格にかなりの影響を及ぼします。
さて、ここまで、4つの原型・アーキタイプを、写真や文章を例にして、特徴を描いてみました。
「原型・アーキタイプ」は、写真を撮る、文章を書く、という異なった種類の「行動」を意味するのではなく、
「動機」を表現します。それは全体の中でになっている「役割」でもあります。
これらの異なる動機・役割をもつ魂が集まっているのが社会です。
それを分かりやすく描くために、「山登り、キャンプをする」ことを考えてみましょう。
「目的地についての情報」を賢者が集めてくると、王は「ルートを確定するのは戦士の〇〇、食料調達は奉仕人の△△」などと「適材適所に配置」しようとし、職人は「山登りとキャンプのための道具、どんな装備が必要か」を考え始め、
僧侶は「誰にとってもよい体験になるように配慮」しようとし、奉仕人は「食料や水などを確保」しようとするでしょう。戦士は「周りが安全か、ルートはどれが一番よいか」を確認しに外へ行き、学者は「あそこであれをやるのは非効率だな。やること観察したことすべてを記録しておこう」と考えるでしょう。
これが「原型・アーキタイプ」があらわす「役割」でもあります。
そのようにして、原型・アーキタイプというのは、人生を通して、転生を通して、その人の動機・役割の底辺に流れるもの、と言えるのですね。
原型・アーキタイプのほかに
「魂の構造」には
「7つのゴール」(今世の霊的な目的・ゴール・フォーカス)
「7つのモード」(今世の性格的資質)
「7つの態度」(経験を処理する方法)
「7つのセンター」(通常の感覚/サイキックセンス)
「7つの錨」(生命の損失を防ぐ安全策)
「7つの魂の年齢・段階」 (前にお話したものです)